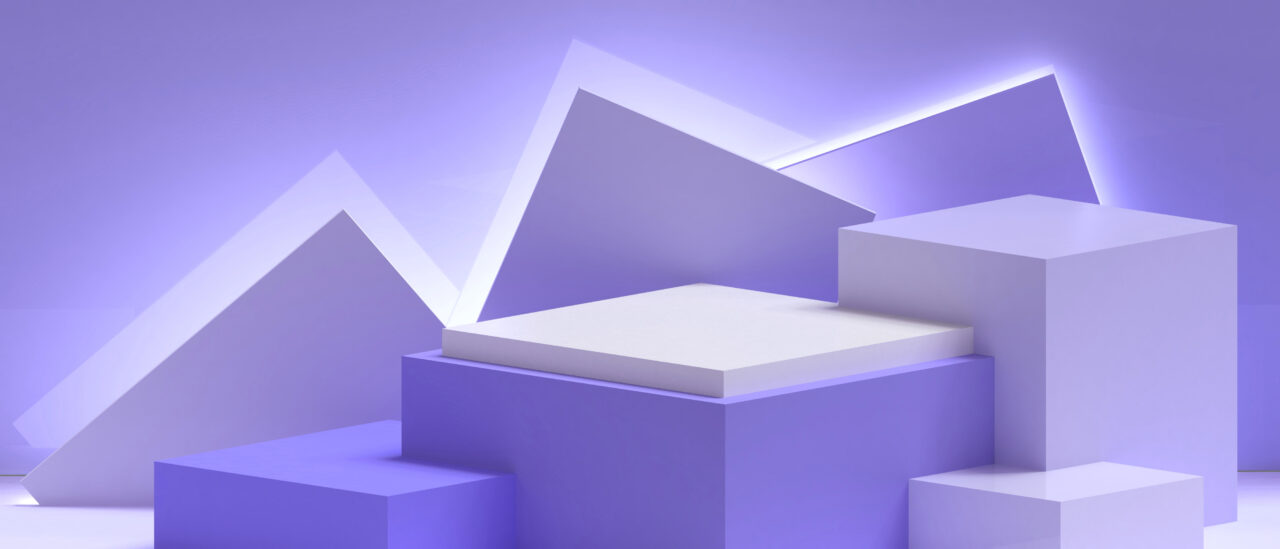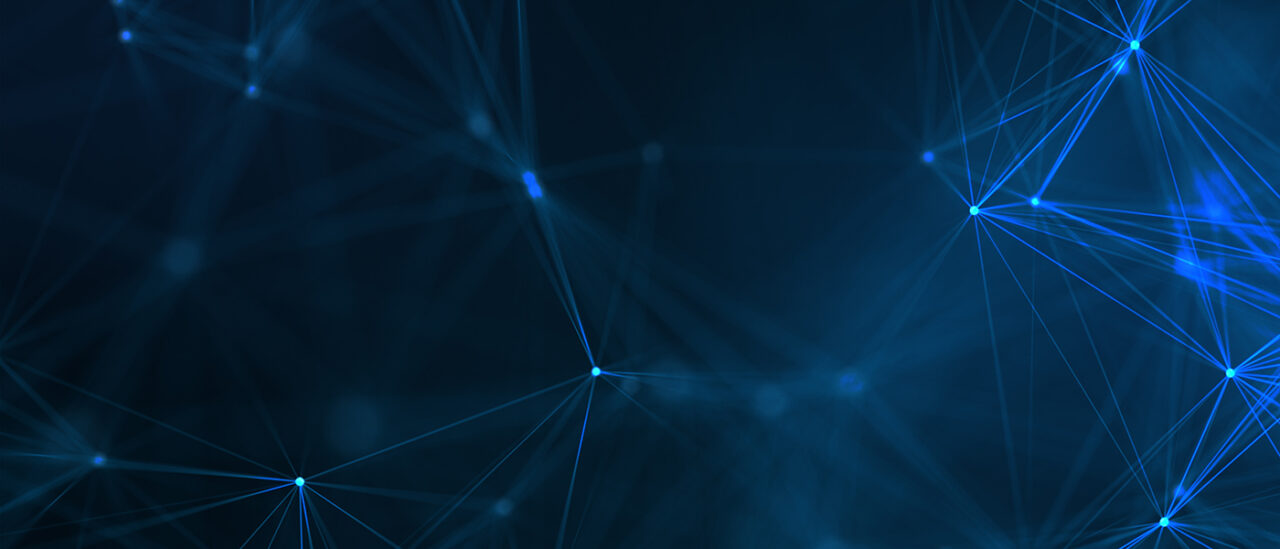熟練した設計者と3D CAD設計者の連携により
貴社にぴったりな設計マンパワーをご提供します。
中小製造業界は、慢性的に人材の確保が難しい状況です。
このようなお悩みありませんか?
✔️ 社員を募集しても働き手が見つからない。
✔️ マッチしたスキルの人材が見つからない。長続きしない。
✔️ 外注に空きがなく、受注を逃してしまう。
もし、エンジニアを必要な時だけ使えたら!
PTOCは、リモート(遠隔)ワークの活用により
ご予算・納期・クオリティをかなえる設計マンパワーを備えています。
また、私たちはお客さまとの信頼関係を構築する業務遂行がモットーです。
お客さまのお困り事に寄り添い、最適なオーダーメイド・ソリューションでお応えします。

3Dモデリング

2D、3Dの組立バラシ

3Dモデリングから部品図作成

設計変更対応

設計にまつわる付帯業務